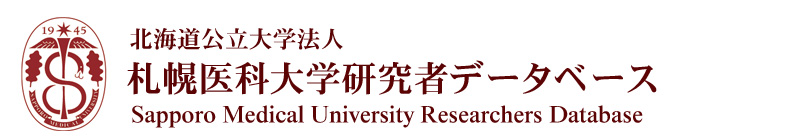研究キーワード
-
血小板
-
アジア
-
新変異型
-
全遺伝子分節
-
遺伝子配列
-
platelet
-
環境因子
-
系統
-
細胞骨格
-
遺伝子型
-
ACME
-
PVL
-
分子疫学
-
SCCmec
-
シグナル伝達
-
全ゲノム
-
市中感染
-
スタフィロコアグラーゼ
-
国際研究者交流
-
遺伝子再集合体
-
ゲノム
-
ストレス
-
ロタウイルス
-
actin
-
リアソートメント
-
環境応答
-
ミャンマー
-
黄色ブドウ球菌
-
MRSA
-
Arf-GAP
研究分野
-
ライフサイエンス / 医療管理学、医療系社会学
-
ライフサイエンス / 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む
-
ライフサイエンス / 血液、腫瘍内科学
経歴
-
札幌医科大学 医学部 社会医学講座 衛生学分野 准教授
2017年7月 - 現在
-
札幌医科大学 医学部 講師
2012年
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
オミックス解析を用いたブドウ球菌 small colony variants の包括的特徴づけ
研究課題/領域番号:24K13443 2024年4月 - 2027年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
漆原 範子, アウン メイジソウ
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
-
アジアにおける高病原性ブドウ球菌の分子疫学および新規病原因子・機序の網羅的探索
研究課題/領域番号:23KK0171 2023年9月 - 2027年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(海外連携研究)
小林 宣道, 漆原 範子, 川口谷 充代, アウン メイジソウ, 大橋 伸英
配分額:21060000円 ( 直接経費:16200000円 、 間接経費:4860000円 )
-
ワンヘルスに基づいた生活環境由来細菌の疫学解析と全ゲノム解析
研究課題/領域番号:21K10417 2021年4月 - 2024年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
漆原 範子, アウン メイジソウ
配分額:3770000円 ( 直接経費:2900000円 、 間接経費:870000円 )
薬剤耐性対策には動物,食品,環境等を含めた分野横断的に取組むこと,すなわちワンヘルスアプローチが重要である。本研究の目的は,生活環境における感染起因菌の分布と薬剤耐性を調査し,ゲノム配列に基づいた比較解析・系統解析を通して耐性遺伝子の進化,及び伝播の様態を考察し,耐性菌の蔓延対策に資することである。
2021 年度は食肉由来の菌体の収集及び解析を中心に行った。札幌近郊の小売店にて購入された鶏肉及び豚由来の 127 株のブドウ球菌属細菌及び Mammaliicoccus 属細菌について 16S rRNA の配列に基づいた菌種の決定および,微量希釈法を用いた薬剤感受性を調査した。菌種をひとつに絞り込めない菌体も多かったため,遺伝系統の近い数種をまとめた species group(Becker k. et al, Clin Microbiol Rev. 2014)として同定した。
鶏肉由来では Cohnii-Nepalensis,Simulans に属するブドウ球菌細菌が多く,豚肉由来菌体では Saprophytics,Warneri が多かった。黄色ブドウ球菌は全体の 4% であった。薬剤感受性試験では,マクロライド系及びスルフォンアミド系の抗生剤に対する感受性が低下している菌体の検出頻度が高かった。マクロライド系抗生剤は家畜の飼料に添加され,スルフォンアミド系抗生剤は治療に用いられることが多い。それらの使用を通じて耐性菌が発生した可能性が考えられた。
Mammaliicoccus 属はブドウ球菌属細菌に共通のメチシリン耐性遺伝子 mecA の起源を染色体ゲノム上に持ち,mecA 遺伝子(群)の進化を考える上で重要である。13 株検出され,5 株が mecA 陽性であった。その中で 3 株は M. fleurettii で,mecA 遺伝子群の構造を決定した。 -
日本とアジアにおける新種・新興薬剤耐性ブドウ球菌の分子疫学と感染制御の基盤構築
研究課題/領域番号:20H03933 2020年4月 - 2024年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小林 宣道, アウン メイジソウ, 川口谷 充代, 漆原 範子
配分額:17680000円 ( 直接経費:13600000円 、 間接経費:4080000円 )
本研究の目的は、薬剤耐性および臨床検査の面で近年注目されている新規ブドウ球菌種S.argenteus、市中感染型MRSA、薬剤耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌について、その疫学的状況を明らかにし感染対策の方策を探ることである。今年度、北海道においては共同研究機関での臨床検体からのS.argenteus、血液由来MRSAの分離保管を行い、その解析を順次進めている。健康成人の口腔に分布するブドウ球菌の研究では、133人の対象者から83株の黄色ブドウ球菌と4株のS.argenteusを分離した。そのうちMRSAは3株で、ST8、ST4775、ST6562の遺伝子型が同定された。ST6562はST8の変異型で、PVLおよびACME遺伝子を有し、米国で優勢なUSA300クローンに類似することが注目された。S.argenteusはST1223、ST2250に型別された。また食肉に分布するブドウ球菌についても、パイロットスタディーを実施し、市販挽肉から分離した黄色ブドウ球菌、コアグラーゼ陰性ブドウ球菌における薬剤感受性と薬剤耐性遺伝子について解析中である。ミャンマーとの共同研究では、ヤンゴン小児病院で小児患者から分離されたMRSA、MSSAの解析結果を論文として報告した。MRSAは約20%を占めST239が主体であり、この遺伝子型は顕著な多剤耐性傾向を示した。MSSAではST121などいくつかの主要な遺伝子型が認められ、いずれも多くの株がPVL遺伝子を有していた。PVL遺伝子は全体で61%と高い検出率が示され、MSSAにおける検出率(68%)はMRSA(35%)よりも高かった。さらにヤンゴン総合病院においても黄色ブドウ球菌の収集を行うとともに、解析を進めている。バングラデシュでは、マイメンシン医科大学附属病院において黄色ブドウ球菌臨床分離株の収集、保管を行った。
-
蛋白結合型ワクチン導入後に分離された 無莢膜型肺炎球菌の薬剤耐性と分子疫学的特徴
研究課題/領域番号:19K10603 2019年4月 - 2023年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
川口谷 充代, 小林 宣道, 漆原 範子
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
本研究の目的は蛋白結合型ワクチンの導入後における肺炎球菌の継続的な分子疫学調査に加え、莢膜を持たない無莢膜型肺炎球菌(NESp: nonencapsulated S. pneumoniae)の分子疫学的・遺伝学的特徴および薬剤耐性を明らかにすることである。本年度は、これまで継続して行なってきた分子疫学的研究の中で得られた遺伝学的知見を考察し、全無莢膜型肺炎球菌株に対して、β-ラクタム耐性に関与するペニシリン(PEN)結合蛋白(PBP)1a、PBP2b、PBP2xのトランスペプチダーゼ(TP)ドメインにおけるアミノ酸変異を分子遺伝学的手法で詳細に解析を行った。解析の結果、PBP1aでは370STMK373のT371S変異(76.0%)と428SRNVP432のP432T変異(71.8%)、TSQF574-577NTGYへのアミノ酸置換(76.0%)が高頻度で見られ、その80.4-81.5%がPEN非感受性株であった。 PBP2bでは442SSNT445のT445A変異(81.7%)が、PBP2xにおいては337STMK340のT338A変異(77.5%)と546LKSGT550のL546V変異(91.5%)が多く検出された。一方、394HSSN397においてH394L変異が見られた多く(83.3%)はPEN感受性であった。TPドメインには様々なパターン、多数の変異が存在していることが特にPBP2xにおいて確認され、NESpにおけるPBP変異には多様性があることを明らかにした。
-
新型エンテロトキシン・病原因子を保有する黄色ブドウ球菌・MRSAの分子疫学
研究課題/領域番号:18K10054 2018年4月 - 2021年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
アウン メイジソウ, 川口谷 充代, 小林 宣道, 漆原 範子
配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )
新型エンテロトキシン(SE)(様)毒素遺伝子について、黄色ブドウ球菌および近縁菌種S. argenteusにおける分布状況と分子疫学的特徴を解析した。selw、selxは調べられた黄色ブドウ球菌の8割以上に検出され、また遺伝子学的多様性が認められた。sey、selzは黄色ブドウ球菌での分布は低率で、sel26、sel27は検出されなかった。S. argenteusのST2250に属する株はすべてseyを持ち、半分以上の株がselz、sel26、sel27を保有していた。新型SE(様)遺伝子の分布は、これらの菌種の遺伝子学的系統(ST)により異なることが明らかとなった。
-
ブドウ球菌属の耐性獲得と水平伝播の背景は?:可動性遺伝因子の構造比較
研究課題/領域番号:18K10055 2018年4月 - 2021年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
漆原 範子, アウン メイジソウ, 小林 宣道
配分額:4290000円 ( 直接経費:3300000円 、 間接経費:990000円 )
ブドウ球菌属細菌は可動性遺伝子エレメント Staphylococcal Cassette Chromosome (SCC)の水平伝播により薬剤耐性をはじめとする遺伝情報を共有し,巧みに環境に適応する。本研究は,SCC の進化・伝播の様式を明らかにすることを目的とし,メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)臨床分離株における SCCの遺伝子配列を決定し,既存の配列と比較構造解析を行った。新たな遺伝子構造を明らかにすると共に,コアグラーゼ陰性ブドウ球菌ゲノムからの水平伝播の可能性,及び形質への影響を考察した。
-
アジア・カリブ開発途上地域における新興薬剤耐性菌の蔓延実態解明と包括的分子疫学
研究課題/領域番号:17H04664 2017年4月 - 2020年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小林 宣道, 鷲見 紋子, アウン メイジソウ, 川口谷 充代, 漆原 範子
配分額:17940000円 ( 直接経費:13800000円 、 間接経費:4140000円 )
病原細菌に関する薬剤耐性の情報が少ないアジア、カリブ地域の3ヵ国(バングラデシュ、ミャンマー、キューバ)において、主要な感染症起因菌(大腸菌、肺炎桿菌、アシネトバクター、黄色ブドウ球菌、腸球菌)の各種薬剤への耐性率、薬剤耐性に関与する遺伝子および病原因子の分布率、薬剤耐性菌の遺伝子学的特徴を解析した。その結果、大腸菌等のグラム陰性桿菌においてβラクタム薬耐性に関わる各種遺伝子が広く分布し、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌において高い病原性に関与する病原因子(PVL)が比較的高率に分布していることが明らかとなった。
-
新規ワクチン開発に向けた肺炎球菌の血清型、薬剤耐性および表層抗原の分子疫学的研究
研究課題/領域番号:16K09101 2016年4月 - 2019年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
川口谷 充代, 小林 宣道, 漆原 範子, 伊藤 政彦
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
2016年6-11月に、北海道各地の医療機関から収集された非侵襲性肺炎球菌729株(小児由来678株、成人由来51株)を研究対象とし、血清型と薬剤耐性、新規ワクチン候補抗原として考えられている肺炎球菌表層タンパク質 A (PspA) の分子疫学的性状を調査した。結果、小児由来株の87.9%がPCV13非含有血清型で、優勢な血清型15A、35B、23Aの81-100%がペニシリン非感受性であった。全菌株の99%がPspA Family 1または Family 2に属していたが、Family 3/clade 6 が非PCV13非含有血清型37(ST447/ST7970)ムコイド型から検出された。
-
ブドウ球菌の動く遺伝因子「SCC複合体」の新規遺伝子構造と分子疫学的性状解析
研究課題/領域番号:15K08781 2015年4月 - 2019年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
漆原 範子, 小林 宣道
配分額:4940000円 ( 直接経費:3800000円 、 間接経費:1140000円 )
ブドウ球菌属の細菌は,可動性遺伝因子 Staphylococcus Cassette Chromosome(SCC)を通じ遺伝情報を共有し,素早く環境に適応する。最もよく研究されているSCCmec は宿主細菌にメチシリン耐性を付与する。SCCmec 以外の SCC にも様々な耐性遺伝子が見られる。本研究では北海道にて分離されたブドウ球菌の SCC の遺伝子構造を解析し,ポリアミン耐性を付与する遺伝子 speG をコードする新規の SCC, 新規の SCCmec 型(XIV 型)を見いだした。さらにその染色体 DNA との結合部位を欠いている SCCmec XIV-like構造を同定した。
-
わが国に出現した新規市中感染型MRSAの蔓延状況と分子疫学的性状の解明
研究課題/領域番号:26460804 2014年4月 - 2018年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
小林 宣道, 鷲見 紋子, 漆原 範子, 川口谷 充代, アウン メイジソウ, 伊藤 政彦, 品川 雅明
配分額:4940000円 ( 直接経費:3800000円 、 間接経費:1140000円 )
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は古くから知られる薬剤耐性菌である。最近日本国内で新たな遺伝子学的特徴を有する2種類のMRSA(①新規遺伝子複合体SCCmec-IVlを持つコアグラーゼIII型MRSA、②皮膚への付着に関連する遺伝子複合体ACMEを有するコアグラーゼII型MRSA)が報告されたため、北海道の臨床分離菌株における分布状況を調査した。①、②は市中・外来患者由来の菌株では各々3.5%、5.1%、大学病院で分離された菌株では3%、0.9% に検出された。ACMEを保有するMRSAには遺伝学的多様性が見られ、それらの市中、病院への拡がりが懸念された。
-
新規網羅的全ゲノム解析法に基づくアジアのロタウイルスの分子疫学と集団流行動態
研究課題/領域番号:25305022 2013年4月 - 2017年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小林 宣道, 鷲見 紋子, 漆原 範子, ゴッシュ ソウビック, 合田 悟, ワン ユアンホン, パウル シャマル
配分額:17550000円 ( 直接経費:13500000円 、 間接経費:4050000円 )
アジアにおけるヒトロタウイルスの長期間にわたる流行動態を全ゲノム(11遺伝子分節)に基づいて分子疫学的に解析した。中国・武漢市で10年以上優勢であったG3P[8]型、その後優勢となったG9P[8]型株では、時間の経過とともに多くの遺伝子分節の系統が変化していた。バングラデシュで優勢なG2P[4]型では、2010年に見られた2つの遺伝学的系統が3年後には新たな別の系統に入れ替わっていた。以上の結果から、ロタウイルス主流行型ウイルス株では、遺伝子分節のリアソートメント(遺伝子交雑)による置換および変異が継時的に起きており、同じ遺伝子型のウイルスでも遺伝子学的には常に変化していることが示唆された。
-
MRSAの新規SCCmec-ACME複合体の遺伝子構造解析と分子疫学調査への応用
研究課題/領域番号:24590751 2012年4月 - 2016年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
漆原 範子, 小林 宣道
配分額:5460000円 ( 直接経費:4200000円 、 間接経費:1260000円 )
The arginine catabolic mobile element(ACME)は,ブドウ球菌ゲノムに見いだされた可動性エレメントである。北海道内の医療機関で分離された MRSA を対象とし, ACME 保有率,ACME 保有菌株の遺伝子的特徴,ACME が挿入されたゲノム周辺の配列を解析した。
ACME 保有率は研究対象期間では有意な上昇傾向にあった。ACME ならびに周辺領域の配列を決定し,新たなバリアントを発見した。さらに北米での代表的な MRSA クローンと同様の遺伝子型を持つ MRSAの増加を確認した。さらにコアグラーゼ陰性臨床分離株でも同様の解析を行った。 -
市中感染型MRSA新興クローンの同定と伝播動態に関する分子疫学的解析
研究課題/領域番号:23590746 2011年 - 2013年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
小林 宣道, 鷲見 紋子, 漆原 範子, ゴッシュ ソウビック
配分額:5460000円 ( 直接経費:4200000円 、 間接経費:1260000円 )
世界的な分布の拡大が懸念される市中感染型MRSA(CA-MRSA)の、日本における分布状況とその分子疫学的特徴を調べるため、札幌医大附属病院での臨床分離株、道内各地の医療機関(外来患者)に由来するMRSAを解析した。その結果、CA-MRSAの遺伝学的指標であるSCCmec type IVおよびVを有する株が札幌医大附属病院で4.3%、道内医療機関で17.1%に検出された。それらの中から米国で優勢なUSA300クローン(ST8 ; PVLおよびACME陽性)と考えられる株を計7株同定したほか、ACMEを有するST5株が多数検出され、それらの新興クローンが日本国内でも分布していることが確認された。
-
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子機序
研究課題/領域番号:22406017 2010年 - 2012年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
小林 宣道, 石埜 正穂, 鷲見 紋子, 漆原 範子, ゴッシュ ソウビック
配分額:19500000円 ( 直接経費:15000000円 、 間接経費:4500000円 )
主としてアジアの国々に分布が拡大している新変異型、新興型ロタウイルスの遺伝学的特徴を明らかにするため、ロタウイルスの全遺伝子配列とその系統解析を行った。中国ではG1P[8]とG3P[8]、バングラデシュではG2P[4]が主要な遺伝子型であったが、それらの中には動物ロタウイルスに由来すると推測される遺伝子分節を有する遺伝子再集合体が検出された。またVP4遺伝子型P[8]の新変異型P[8]bは中国、バングラデシュ、ミャンマーで検出され、世界的な新興型G9を伴うものが多かった。アジアおよび他の地域からの様々な新興型ロタウイルス(遺伝子型G1P[6], G2P[6], G3P[2]、G3P[6], G3P[9], G4P[10], G6P[9], G8P[1], G9P[19])の全遺伝子を解析したところ、それらは1)ヒトロタウイルスの異なる遺伝子群間の遺伝子再集合体、2)ヒトと動物ロタウイルス間の遺伝子再集合体、3)動物ロタウイルスが直接ヒトに伝播したと考えられるもの、に大別された。以上より、新変異型、新興型ロタウイルスのおもな出現機序は、遺伝子再集合と種間伝播であると考えられた。
-
新規分子疫学的手法を用いたPVL陽性黄色ブドウ球菌・MRSAの蔓延状況の解明
研究課題/領域番号:20590608 2008年 - 2010年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
小林 宣道, 石埜 正穂, 鷲見 紋子, 長嶋 茂雄, 漆原 範子
配分額:4810000円 ( 直接経費:3700000円 、 間接経費:1110000円 )
北海道内の医療機関において外来患者に由来する多数の黄色ブドウ球菌を対象とし、メチシリン耐性菌(MRSA)の分布状況とその分子疫学的特徴を解析した。その結果、市中感染型MRSAの典型的な特徴であるPanton-Valentine Leukocidin(PVL)遺伝子を保有するMRSA(遺伝子型ST6,ST59)、米国で優勢なUSA300クローンに特徴的な遺伝性因子ACME を持つMRSAが数株検出され、これらのMRSAの市中における拡がりが示唆された。
-
血小板低分子量Gタンパク調節因子研究の創生
研究課題/領域番号:19591092 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
小田 淳, 漆原 範子, 漆原 範子
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
現在, 日本国民の関心の高い生活習慣病がなぜ問題であるかというと, 心筋梗塞などの病的血栓症の原因になるからである. 病的血栓症の発症に中心的な役割を果たすのが, 血小板である. そこで, 血栓症の治療に血小板の機能を抑制する薬物(抗血小板薬)が使用される. しかし, その効果は限定的である. 血小板の機能は複雑なシグナル伝達によって制御されている. この複雑なシグナル伝達の解明は新たな抗血小板薬の候補探しに有用であることが期待される. 本研究の理念はこのようにわが国の病的血栓症治療に基礎的に貢献することである. 具体的には, どの細胞でも重要な低分子量Gタンパクとその調節因子に関する研究を進め, 低分子量Gタンパクracの下流に位置するタンパクWAVEが血小板の伸展に重要なことを明らかにし, また, 別の低分子量Gタンパクarfの調節因子GIT1のNckによる新たなリン酸化機構を明らかにするなど, 研究目的に沿った研究成果を挙げた.
-
ストレスの定量的評価の試み
研究課題/領域番号:19659147 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 萌芽研究
藤田 博美, 小田 淳, 若尾 宏, 漆原 範子
配分額:3300000円 ( 直接経費:3300000円 )
成果の一部を上げる. まず, ニジマス由来RTG-2細胞の環境ストレスに対する応答を解析した. 化学汚染物質トリブチルスズ(TBT)がRTG-2にMAP kinase (ERK, JNK, p38 MAP kinase)の活性化を惹起すること, caspase活性化を伴うapoptosisを誘導することを明らかにした. さらにJNKがTBTによるcaspase依存的なapoptosisに, p38 MAP kinaseがcaspase非依存的な細胞死に関与することを明らかにした. 更に熱ショックに対する応答の解析を行った.
次に, 生物進化の過程でヒトを含めて広く保存されてきた様々な環境ストレスに対して共通する検知・応答機構について, 細胞骨格と細胞接着に注目して検討を進めた. 即ち, 良く保存されているArf-GAPタンパクGIT1とアダプタータンパクNckの結合様態と生理的意義について, 分子細胞生物学的な検討を行い, GIT1のチロシンリン酸化がNickを結合パートナーとして細胞内局在の移動をもたらし細胞機能を発揮していることが示唆された. これらのタンパクは線虫から哺乳動物まで重要な役割を果たしており, 普遍性の高いものであることが推察される. -
血小板に新規同定されたシグナル分子の生理的意義の解明
研究課題/領域番号:17590976 2005年 - 2006年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
小田 淳, 中山 章, 漆原 範子
配分額:3500000円 ( 直接経費:3500000円 )
血小板機能制御の分子レベルの理解が深まることは,新規抗血小板薬の開発にも大変有用であることが期待される.最近,これまで血小板で報告されてこなかった分子が次々に同定されている.これらの分子は単に基礎的に興味深いばかりではなく,将来の抗血小板薬のターゲット候補となりうる.17年度においては,血小板の関与するアクチン重合に関連するWAVEタンパクのアイソフォームの全て(WAVE1-3)が存在し,さらにこのWAVEと結合するSra-1,Nap-1,Abi-1などが血小板にあることを初めて報告した(Blood, 2005).18年度では,主として培養細胞を用いてIRSp53とWAVEさらにSra-1, Nap-1の関連性に関して検討を加えた(J Cell Biol, 2006).この報告で,IRSp53が改めて低分子量Gタンパクracの下流でWAVEの機能に重要な役割を果たしていることを確認した.血小板にもIRSp53が存在することは確認しており,血小板アクチン重合にもracの下流でIRSp53・WAVE系が重要な役割を果たしていることが想定される.実際、東京大学医科学研究所 江藤浩之博士らとの共同研究においてマウスの巨核球レベルでは,この想定を支持するデータが得られ,2006年度の日本血液学会総会などで,共同発表した.さらに,血小板にも存在することが全く報告の無いWAVE2結合タンパクのHEM-1に関して特異抗体を作製し,これが血小板に存在することを確認した.以上のように,血小板で新規にタンパクを次々に同定し,かつ必要に応じて特異抗体を作製,また核の無い血小板では容易に出来ない実験に関しては細胞株やマウス巨核球を用いてその分子の生理的意義を検討した.以上のように,将に当初の研究計画書どおりの幅広い手技を駆使して,予想通りの成果を挙げえた.